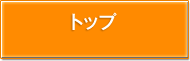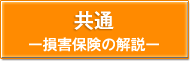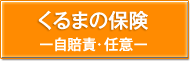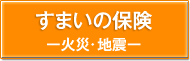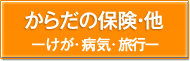| 解説 | ②保険料と税金の関係 |
|---|
「地震保険料控除の対象となる損害保険契約」で支払った保険料の一定額を差し引くことができる「地震保険料控除制度」があります(注1)。
「地震保険料控除の対象となる損害保険契約」とは、「地震保険」と「経過措置が適用される長期損害保険(注2)」になります。
「地震保険」の保険料控除の対象は、保険料を支払っている者またはその者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用建物・生活用動産を保険の対象とするものに限られています。
「経過措置が適用される長期損害保険」の保険料控除の対象は、保険期間が10年以上で満期返戻金のある損害保険契約で、2006年12月31日までに契約した場合、かつ、2007年1月1日以後に保険料が変更となる異動がない場合の保険としています。
地震保険料控除制度により、所得税は最高50,000円を、住民税は最高25,000円を所得金額から差し引くことができるようになりました。また、「経過措置が適用される長期損害保険」の保険料控除は、所得税について最高15,000円、住民税について最高10,000円を所得金額から差し引くことが認められています(注3)。
ただし、地震保険契約と長期の損害保険契約の両方がある場合には合算して所得税は50,000円、住民税は25,000円が限度となります。
なお、従来の火災保険などの損害保険料控除制度(所得税について最高控除額15,000円、住民税について最高控除額10,000円)は廃止されております。
注1 所得税法第77条
注2 経過措置が適用される長期損害保険の保険料は、地震保険の保険料ではありませんが、控除制度の名称は地震保険料控除になります。
注3 2006年法律10号改正附則10および取引等に係る税務上の取扱い等に関する国税庁への文書照会結果(2006年12月27日回答)
地震保険料控除制度の保険料控除限度額は、下表のとおりとなります。
- 所得税の場合
| 区分 | 1年間の支払保険料(注2)の合計 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料(A) | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 | |
| 旧長期損害保険料(B) | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 10,000円超 20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
| 20,000円超 | 15,000円 | |
| (A)と(B)の両方がある場合(注1) | ― | (A)(B)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
- (注1)
- (B)に(A)が付帯(セット)された(または中途付帯された)契約においては、(A)か(B)のいずれか一方を選択して適用を受けることができます。
- (注2)
- 1年間の支払保険料とは、その年の「1月1日から12月31日まで」に保険会社に支払った保険料から、保険会社から受領した返れい金等を控除したものをいいます。
- 個人住民税の場合
| 区分 | 1年間の支払保険料(注2)の合計 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料(A) | 50,000円以下 | 支払金額×1/2 |
| 50,000円超 | 一律25,000円 | |
| 旧長期損害保険料(B) | 5,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 5,000円超 15,000円以下 |
支払金額×1/2+2,500円 | |
| 15,000円超 | 10,000円 | |
| (A)と(B)の両方がある場合(注1) | ― | (A)(B)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円) |
- (注1)
- 上記 所得税の(注1)に同じ。
- (注2)
- 上記 所得税の(注2)に同じ
例えば、所得税率20%、個人住民税率10%とすると、地震保険料控除により所得税で10,000円(50,000円の20%)、個人住民税で2,500円(25,000円の10%)税負担が軽減されます。
控除を受けるためには、各保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」もしくは「損害保険料控除証明書」を、「課税所得の確定申告書」または給与所得者の年末調整の際の「保険料控除申告書」に添えて所轄税務署に提出する必要があります。