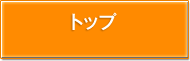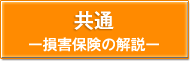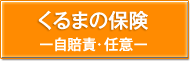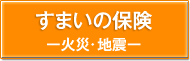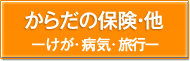| ��55 | �Еی��̕ی����z�͂ǂ̂悤�ɐݒ肷��悢�̂ł����B |
|---|
- ����
- �ی��̑ΏۂƂȂ錚����ƍ��̕]���z����ɕی����z��ݒ肵�܂��B������̏ꍇ�ɏ\���ȕ⏞���邽�߂ɂ́A�K���ȕ]���z�Ɋ�Â��ی����z��ݒ肷��K�v������܂��B
�Еی��̌_��ɂ������ẮA�����܂��͉ƍ��Ƃ������ی��̑ΏۂƂȂ�u�����v�𐳂����]������K�v������܂��B�Ȃ��Ȃ�A�Еی��̕ی����z�́A�_�̕]���z����Ƃ��Đݒ肷�邩��ł��B
������ƍ����������]�����ꂸ�K���ȕی����z�̐ݒ肪�Ȃ���Ȃ��ƁA���Q�z�ǂ���̕ی������x�����Ȃ��ꍇ������܂��i�u��56�v�Q�Ɓj�B
�����̕]���z�͔N���̌o�߂ƂƂ��ɕϓ����܂��̂ŁA�_����������Ƃ������łȂ��A�_����X�V����ۂɂ��A�K�v�ɉ����āA�ی����z�����������Ƃ��K�v�ł��B
�i�ی����z�̐ݒ���@�j
�Еی��̕ی����z�͓K���ȕ]���Ɋ�Â��ݒ肵�܂��B�]���ɂ͍Ē��B���z�i�V���j��Ǝ����z���2�̊������܂��B
�u�Ē��B���z�v�Ƃ́A�ی��̑ΏۂƂȂ�u�����v�Ɠ����i�����\���E�p�r�A���A�K�͂Ȃǁj�̂��̂������_�ōĒz�܂��͍čw�����邽�߂ɕK�v�ȋ��z���x�[�X�Ƃ����]���z�ł��B�u�����z�v�Ƃ́A�Ē��B���z����o�N�E�g�p�ɂ����Օ��i�����j���������������z���x�[�X�Ƃ����]���z�ł��B
�u�Ē��B���z�v�Ɓu�����z�v�̊W���Z���Ŏ����ƁA���̂Ƃ���ƂȂ�܂��B
�����z�@���@�Ē��B���z − �o�N�����z�i�o�N�E�g�p�ɂ����Օ��j
�k��L�Z���̕⑫�����l
��ʓI�ȌX���Ƃ��Ă͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA�Ē��B���z�͏㏸���A�����z�͉������Ă����܂��B�������A�����̏㏸���ɂ͎����z���㏸���邱�Ƃ�����A�����̉������ɂ͍Ē��B���z���������邱�Ƃ�����܂��B
�����z����ɕی����z��ݒ肵���ꍇ�A���Q�z�͎��̔������̎����z����Ƃ��ĎZ�o����邽�߁A�ی��������ł͓������������Ē������蔃���ւ����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�\��������܂��B
���̂悤�Ȗ����������A�ی��������Ō��Ē������蔃���ւ�����ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�ی����z���Ē��B���z�Őݒ肷����@���p�ӂ���Ă��܂��B���݂ł́A�Ē��B���z�̕]���z���x�[�X�ɕی����z��ݒ肷��_��ʓI�ƂȂ��Ă��܂��B
�i�]���̕��@�j
�������]���z���Z�o���邽�߂ɂ́A�����̌��z���z�A���z�N�A�����ʐρA���ю�̔N��A�Ƒ��\���Ȃǂ̏�K�v�ɂȂ�܂��B�����̏��Ɋ�Â��A���̕��@�Ō�����ƍ��ɂ��Ă̕]���z���Z�o����̂���ʓI�ɂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�����̏ꍇ�A�]�����_�ŐV�z�����ł���A���̌��z���z���]���z(�Ē��B���z)�ƂȂ�܂��B�������A���z���z�ɓy�n��͊܂܂�Ȃ����ƂɂȂ�܂��̂ŁA�s���Y�̍w�����z����y�n������������悤�ɗ��ӂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
�V�z�����łȂ��ꍇ�ɂ́A���̌�����V�z�����N����ѓ����̌��z���z���������Ă���A�V�z���_���猻�݁i�]�����鎞�_�j�܂ł̔N���ʎw���i���z��{���j���悶�čĒ��B���z���Z�o������@������܂��i������u�N���ʎw���@�v�܂��́u�Ď擾���z�@�v�ȂǂƂ����܂��B�j�B
�Ē��B���z�@���@���z���z�@�~�@�N���ʎw���i���z��{���j
- ��
- �����z�x�[�X�̕]���z���Z�o����ꍇ�ɂ́A�o�N�E�g�p�ɂ����Օ������������܂��B
����ɑ��A�V�z�����N�ⓖ���̌��z���z��������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����Ɏg���Ă���ޗ��ȂǂŒ�߂�ꂽ�u1�u������̐V�z��P���v�Ɍ����̉����ʐς��悶�čĒ��B���z���Z�o������@������܂��i������u�V�z��P���@�v�܂��́u�T�ϖ@�v�ȂǂƂ����܂��B�j�B
�Ē��B���z�@���@�V�z��P���@�~�@�����ʐ�
- ��
- �����z�x�[�X�̕]���z���Z�o����ꍇ�ɂ́A�o�N�E�g�p�ɂ����Օ������������܂��B
�ƍ��ɂ��ẮA���L���Ă���ƍ��̋��z��ώZ����̂���{�ƂȂ�܂����A���̕��@�ł��Ɖƍ��ЂƂЂƂ�]�����Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ�̂ŁA���ԂƎ�Ԃ������邱�ƂɂȂ�܂��B�����������Ƃ����Ă̂����A���ȕւȕ��@�Ƃ��Đ��ю�̔N���Ƒ��\���Ȃǂɉ����ĕ��ϓI�ȕ]���z�����߂���@���p�ӂ���Ă��܂��B